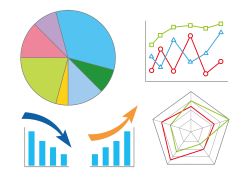
統計と心理学には、どのような関係があるのでしょうか
【目次】
日本では365日の全てに何らかの記念日が制定されています。1月29日は「人口調査記念日」に制定されています。これは、1872年の1月29日に明治政府による日本初の全国戸籍調査が実施されたことがきっかけとなっています。この戸籍調査は前年の1871年の戸籍法に基づいて実施されたものであり、1872年に編製されました。
日本の戸籍制度は、645年の大化の改新からスタートしたと考えられており、大化の改新の際の公地公民制による口分田を基礎に年貢を徴収するために国民を登録するようになった制度が戸籍の前身と考えられています。戸籍は編製年の干支である壬申から壬申戸籍ともよばれています。この当時の人口は男性が1679万6158人、女性が1631万4667人の合計3311万825人となっていました。現在よりも、約1億人少ないことになります。戸籍調査は人口統計に関する基本的な調査であると考えることができます。
では、統計調査と心理学には、どのような関係があるのでしょうか。
心理統計学は大学の学部でも必修の内容であり、心理カウンセラーが科学者としての視点を持ちながら活躍するためにも重要なものです。大学の心理学科で必修の科目であり、公認心理師になるためにも必須の授業科目となっているものに、心理統計学があります。たとえば、心理カウンセリングにおいて、クライエントの抱える問題が改善・解決したとします。そこで「良くなったのだから、それでいい」ではなく「なぜ、良くなったのか?」について、しっかりと科学的な観点から捉えなければなりません。そのため、なぜ、このような結果になったのか、この結果から、どのようなことが考えられるのか、結果を基に、どのような対策を実施すべきか、などについて考える必要があります。
これはカウンセリングが上手くいっていても、上手くいなくても、どちらにしても考えなければなりません。偶然に上手くいっただけであれば、それは「次も上手くいく保障はない」ということを意味します。そして、上手くいっていないのであれば「どうすれば現状から変化させて、上手くいく方向に転換できるのか?」について、論理的に考察する必要があります。カウンセリング・アセスメントにおける様々なデータは、適切に分析・処理することで、はじめて有益な情報となります。クライエントがカウンセリング中に述べたことは全て“情報”です。また、心理検査などの結果も全て“情報”です。しかし、これらは心理カウンセラーが分析・処理しなければ“ただの情報”でしかなく、問題の改善・解決のための「役に立つ情報」とはなりえません。こういった情報を「科学的に」「正確に」「分かり易く」扱う際に重要となってくるのが、心理統計学的な分析・処理なのです。統計的な分析をすることで、出来事や現状はより明確により分かり易くなります。また、平均値や中央値、最頻値などの様々な代表値を算出することは、心理専門職にとっても重要になります。
また、平均値や中央値・最頻値を算出しただけでは、データの偏りやバラつきが分からないこともあります。たとえば、多くのデータの中の1人のデータが大きく偏っていると、それに引きずられて、全体平均が変化してしまいます。しかし、これでは平均値や中央値、最頻値が全体像を反映しないものになってしまいます。そこで、標準偏差(SD)を算出することで、個別のデータが全体の中のどこに位置づけられているかを確認することができます。
これらはあくまで一例ですが、考え方として「数値を論理的に読み取り、理解する」というクセがついていることが、心理カウンセラーとしての活動に非常に重要となるのです。苦手意識がある人も多いかと思いますが、心理統計学は「事実を見抜く」ということにおいて、とても大切なものなのです。
この記事を執筆・編集したのはTERADA医療福祉カレッジ編集部
「つぶやきコラム」は、医療・福祉・心理学・メンタルケアの通信教育スクール「TERADA医療福祉カレッジ」が運営するメディアです。
医療・福祉・心理学・メンタルケア・メンタルヘルスに興味がある、調べたいことがある、学んでみたい人のために、学びを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。